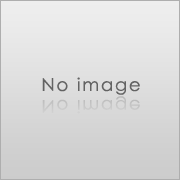

| 名前 | 勇 (イサミ) |
|---|---|
| 職業 | 薙刀士 |
| 生年月日 | 1018年 ??月 〜 1019年 6月 |
| 当主経験 | 2代目当主 |
| メモ | 初代当主の第一子。 後に『始祖の五兄弟』と呼ばれるはじまりの子供達の長兄、すべてのはじまりの子。 身長は170cm。 痩せ細ったモヤシ体型。 天界側としても初の試みであった『交神の儀』。 その儀式によって誕生する命の、謂わばプロトタイプとも言うべき存在。 だが、儀式は実験段階の不完全なもので、そんな不完全な儀式によって誕生した彼は、明らかに歪な命であった。 少し走っただけで息は切れ、鬼共を一刀の元に斬り伏せる事も難しい。 後に生まれた弟はもちろん、妹にすら劣るほど痩せ細った貧相な肉体。 あまりにも不完全で脆い、力と肉体。 黄川人の言葉を借りて言うならば、そんな不完全で出来損ないの肉体も、戦の経験を積めばそれなりに格好は付いた。 だが… 母の方が青ざめるほどの大怪我を負っても一片の痛みも感じず、鬼の爪牙を前にしても恐怖すら感じない。 荒れ果てた京の都のドブ川に浮き沈みする屍を見てもその心に僅かな波すら立つ事無く、笑いもしなければ涙も溢さない。 そう、彼には心が無かった。 人として当たり前の感情が、一欠片すら無かった。 『交神の儀』は未だ実験段階だった。 彼という歪な命を実例として生み出した事で、ようやく完成した。 はじまりの子は、実験台だった。 それに気付いた母である初代当主は、自分の復讐の為に取り返しのつかない過ちを犯した事を悟り我が子に泣いて詫びるが、心の無い勇には、何故母が泣いているのか分からなかった。 だが、どうやら自分は異常らしいという事だけは聡く察した彼は、母やきょうだいが異質な目で見られぬよう、表面上は使命を恐れる事無く受け入れる気のいい好青年を演じる事にした。 そんな彼が変わり始めるきっかけとなったのが、弟・竜元の指導に当たる母に代わって妹・佑喜と共に赴いた鳥居千万宮出撃だった。 恐れを感じない彼は、奥へ奥へと突き進む内に、一回り強大な燃え髪大将と遭遇する。 そして、燃え髪大将の『花連火』に焼かれ、危うく死に掛ける。 幸いにして敗走には至らず、決死の踏ん張りにより何とかその場を切り抜けるが、間も無く勇は意識を失い、しばし現世と彼岸の境目をさ迷う。 やがて意識を取り戻した彼が最初に見たのは、佑喜の泣き顔だった。 「どうした、佑喜。どこか、怪我をしたのか」 「ちが…違い、ます…!」 「痛くもないなら、何故泣いている」 「だってお兄様、酷い火傷で…このまま目を覚まさないかと…! お兄様が目を覚ましてくれたのが、嬉しくて、安心して…!!」 「…?嬉しいのに、何故泣く」 「ふふ…お兄様ったら変なの。 嬉しい時も泣くのが、人間じゃないですか」 「…そうか。嬉しい時も、涙を流すのか。 なら、きっと俺も今、嬉しいんだろう」 「ええ、きっとそうですよ。 だってお兄様も、泣いているもの」 …その一件以来、勇は彼なりに、心を学び始めた。 母を真似てきょうだいの頭を撫でる。 そうして照れたり嬉しそうにするきょうだいを見ると、胸が温かくなる。 これが『愛しい』。 鴨川のほとりに家族みんなで散歩に出る。 はしゃぎ回るきょうだい達に付き合っていると、胸が弾んでくる。 これが『楽しい』。 きょうだいが驚いた様子を見せる。 どうしたのかと聞けば、今笑ったかと問われる。 頬に触れれば、口角がいつの間にか上がっていた事に気付く。 これが『笑顔』。 家族やイツ花と触れ合う時間が、彼の空っぽの心を鮮やかに彩っていった。 乏しいながらも、彼の顔には少しずつ表情や感情が芽生えていった。 だが、学んだのは温かな感情だけではなかった。 夕飯時、狙っていた煮物の芋。 それを弟に横からひょいと取られた時、胸の奥がむずむずと渦を巻いた。 これが『悔しい』。 感情が乏しいゆえに存在感が無い。 だからきょうだい達になかなか気付かれなかった時、胸の奥がチクリと痛んだ。 これが『寂しい』。 都と共に荒れ果ててしまった民の心。 いわれの無い罵声に家族が晒された時、父から譲り受けた火が胸の奥を焦がしたのを感じた。 これが『怒り』。 ……当主ノ指輪を託した母の手が冷たくなっていき、母の目が開く事は二度と無いと分かった時。 双眸から自然と涙が溢れ、止まらなくなった。 胸の奥がひりひりと痛んだ。 これが……『悲しい』。 そして。 命の灯に陰りが見え始め、母から受け継いだ血を繋げるべく交神の儀を執り行った際。 彼は二つの大きな感情を知った。 交神相手である みどろ御前 に、勇はぽつぽつと懸念を口にする。 生まれ来る我が子は、ちゃんと心を持って生まれてきてくれるだろうか。 生まれ来る我が子を、自分はちゃんと父として愛してやれるだろうか。 そんな彼に、みどろは優しく笑いかける。 『そう思い悩む時点で、貴方は我が子を愛している』。 『だからきっと、その愛は生まれ来る子に豊かな心を授けてくれる』と。 その言葉に、勇は生まれ来る我が子を愛せているのだと安堵する。 そして同時に、これが『愛する』という感情なのだと学ぶ。 だが同時に知る。 「今は、何もかも忘れて…」 忘れる。 忘れたら、何もかも無くなってしまう。 なら、人が忘れられたら? 母のように長く当主を務めた訳でも無ければ、佑喜達のように目立った戦果を残した訳でもない。 そんな俺を、皆は覚えていてくれるだろうか。 そんな俺を、皆は忘れないでいてくれるだろうか。 皆に忘れられたら、俺は、どうなってしまうだろうか。 そう考えた勇の胸を、得体の知れない冷たい何かが包んで捉えて離さなかった。 心臓が早鐘のように鼓動を打ち、震えが止まらなかった。 嗚呼、これが……『恐怖』。 大切なきょうだいに忘れられる事。 それが、心無き歪な存在だった勇が唯一覚えた恐怖だった。 「誰か俺のこと、『忘れない』って言ってくれ…」 それが、勇の最期の言葉だった。 勇は、生きて我が子を迎えられなかった。 遺されたきょうだい達は、兄の最期の懇願を忘れなかった。 兄の事を永遠に覚え続ける事を誓った。 その思いを込めて、兄の忘れ形見である幼子にきょうだいはこう名付ける。 『勇』よ『永』久に。 ──『勇永』。 |